好きと嫌いと

味がなくて、モサモサしたものを好む傾向がある。
その代表としては、プレーンなスコーンや、薄味のグラノーラ、ベーグルなど。穀物味がつよく、オーソドックスな味わいのやつ。
最近ではおからのクッキーにハマっていて、作ったほうが早いのではないかということで、ときどき家で作っている。
このおからクッキーは、わたしは美味しい!!!と思って食べているのだけれど、おそらく一般的には全然美味しくなくて、ゴリゴリするほど硬くて、味はなく、食感だけがやたら主張している。それなのに、食べだすと止まらない。
おからクッキーが好きすぎる。好きすぎて、嫌い。
好きすぎて、永遠に食べてしまうから、嫌い。飽きがこなさすぎて怖い。そんなに食べたくないのに、なんか食べちゃう、みたいな。気付いたらうっかり食べてた!みたいな。
欲求をコントロールできないくらい好みのものに対して、ちょっと嫌い、というパラドックス。
”好き”と”嫌い”が遠く離れた別物ではなくて、好きの中に嫌いを内包している、という感じがする。
逆に、嫌いなものが好きを内包していることもある。嫌いという感情を湧き起こす心の動き自体は好き、というパターン。
こうなると、好きとか嫌いを判断するのは難しいような気がしてくる。好きなことをしなさい、と言われても、その好きは嫌いを含んでいるかもしれないし、嫌いの中に存在する好きのことを好きだと認識しているかもしれない。身体のことばと頭の言葉、つまり感覚的なことばと思考的な言葉がズレている気がする。
そうであるならば、頭の中の言語をいったん捨てて、好きと嫌いを決めずに、身体の心地よさを頼りすることがとても大切なように思える。
心地よいことを、心地よいまま、身体に委ねる。好きか嫌いかは、特に決めない。
好き、嫌い、という言葉は端的で伝わりやすいけれど、言葉が強いだけに自分をも洗脳してしまうような気もする。
”わたしはおからのクッキーが好きです”を、”わたしはおからのクッキーを永遠に食べてしまうタイプの人間です”に変えてみるとどうか。
事実を事実のまま伝えるには、こっちの方がしっくりくるような気がしてくる。
”わたしはコーヒーが好きです”を、”わたしは街でコーヒーを淹れることがやめられないタイプの人間です”というほうが、なんだかしっくりくる。
”わたしは人が好きです”は、”わたしは人の話を聞くことで満たされるタイプの人間です”という方がより事実に近い。
好きと嫌いを封印すると、別の伝え方がみえてきてちょっとおもしろい。
というような話を息子にして、君はどう?と尋ねてみたら、「おれは好きなものは好きで永遠に望んでいて、欲していて、そこに対して嫌いも恐怖もない!」とのこと。きっと、頭の言葉(思考の言葉)が邪魔していない状態なのかもしれない。
シンプルな状態で産まれ、ごちゃごちゃと色々なものを身につけ、また最後には不要なものはすべて削いでシンプルな状態になれたらとてもいい。私は、まだ削ぐものがたくさんありそうだと実感しました。
今週は、豊田市ではラリーが行われ、6日〜9日までいろいろなところで交通規制がかかりそうです。いつもの駅前がちょっと雰囲気が変わっての賑やか営業になりそうです。若干イレギュラーなので、営業時間などはまたインスタストーリーなどでその都度流せれたらと思います。
そんなわけで、今週もがんばりましょ〜!◎
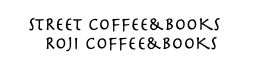





好きなものは人それぞれ
妻は揚豆腐にスライスした玉ねぎを乗せチーズをトッピングしてオーブンで焼く「それ」が好きで、良く食卓に出てくる
私の分も用意してくれるが、あんまり好きじゃないから残すと「それ」を次の日の弁当のおかずとして持っていくʬ
もう自分専用のおかずにしといてくださいʬ
好きな「もの」、「人」、「音楽」等々、なんで好きなのかは上手く説明できないけど「好き」なものは好き!としか言えない
「好き」が沢山ある事は幸せなんだと思う
「好き」を使わずに説明するの面白い
「受け入れちゃう」、「心地よい」、「吸収したい」、「その状態を続けたい」…って事が「好き」って事なのかしら?