楽しいの温度

楽しい、というのは何度くらいなのだろう。
95度、沸騰寸前みたいなぶわ~っと湧き上がってくるものを”楽しい”と呼んでいる人もいれば、40度、いい湯加減みたいな”楽しい”が好みの人もいる。
40度は、ある人にとっては楽しい、だけれど、別のある人にとっては”退屈”かもしれない。95度はある人にとってはエキサイティングなものであっても、別のある人にとっては刺激が強すぎて”苦痛”にもなりえる。
反対に、楽しくない、というのはどのくらいのことなのだろう。
例えば、嫌いな食べ物の”嫌い”とはどれくらいのものなのか。好んでは食べないけど一応食べれる、というのは”嫌い”にはいるのか。見ることもできないくらい嫌悪感のあるものだけを”嫌い”と呼んでいるのか。
好き・嫌い、という二項で好き嫌いを語るのか、好き・ふつう・嫌いという三項で好みを語るのか、それぞれの分布の割合はどのくらいづつなのか、もっとグラデーション的な無段階で言っているのか。状況に応じてその個体の好きと嫌いは横断するのか、絶対的なものなのか。
良い、悪い、はどうか。白と黒で切り分けられないようなことは、どのあたりまで”良い”になり、どのあたりからは”悪い”になるのか。真っ白ということも、真っ黒ということも、ありえないのではないか。だとしたら、すべてはグレーである、と言ってもいいのか。絶対的な良いなどありえないとしたら。
ある人にとっては”いい人”で、別のある人にとっては”いい人とはいえない”というのが通常だとしたら、その人自体は”いい人”ともいえるし、”いい人じゃない”ともいえるし、そのどちらでもあってどちらでもない、ともいえる。
そうなると、『いい人』というのはこの世界に存在しなくて、『悪い人』というのもこの世界に存在しないのではないか。あくまで枕詞に”私にとっては”や、この側面から見たら、という一言が必要になってくるのではないか。
そういったいちいちを面倒くさく掘っていくと、そもそも、日本語話者だからといって同じ言語で話しているというのはきっと勘違いで、本当は通訳が必要なくらい異なる言語で話している、と思っておいたほうがいいのではないか、とずっと思っている。
、、、とはいえ。
95度の楽しさを話している人と、40度の楽しさを話している人が、本当は同じものを共有してはいなかったとしても、共感しているという思い込みが人を救うこともある。ボタンがかけ違っていたなどという事実は、知らなくていいことなのかもしれない。
言語に対して、ずっと懐疑的だ。
だから、それを扱っている”人間”に対してずっと興味があって、飽きなくて、慣れなくて、ずっと楽しい。この楽しいの温度はきっと、小春日和。25度くらいなのだろうなあと思う。
関連記事
コメント4件
温度の話なので食いつかずにはいられない!
絶対と相対は温度だとわかりやすいですね。
40℃のお湯、25℃のぬるま湯、10℃の冷水が入った3つのバケツがあって、最初に40℃と10℃のバケツに左右の手をそれぞれ入れた後に、両手を25℃のバケツに入れると、片手は暖かく感じるのに片手は冷たく感じる。どちらも自分の手なのに。。という実験を小学生にすると結構盛り上がります。この時は外気温と室温の関係の話に繋げるけど、「状況によって感じ方は変わる」という解釈にも繋げられると思ってます。
あと前も書いたけど、個人的には言語化するのは好きで、仕事でもしなきゃいけないことだけど、「言語化」とか「定義づけ」とか「見える化」とかって、相手の創造力や思考力を奪う行為でもあると思います。嫌な言い方をすれば「バカ化」を促進させる。その方が都合がいい時は特に。
理想は相手との信頼関係が成り立っていて、自由に発想して、それをお互いに尊重し合えることだと思いますが、まぁ、なかなか難しいですよね。
だから、
「そもそも、日本語話者だからといって同じ言語で話しているというのはきっと勘違いで、本当は通訳が必要なくらい異なる言語で話している、と思っておいたほうがいいのではないか、とずっと思っている。」
にもメチャメチャ激しく同感です!
もう、全国民が通訳介した方が平和になるのかもと思うくらい(笑)
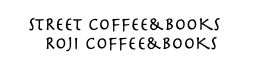



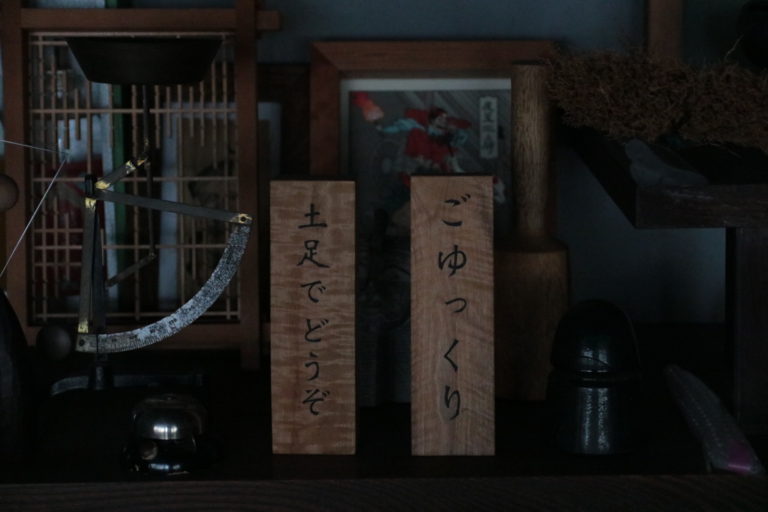
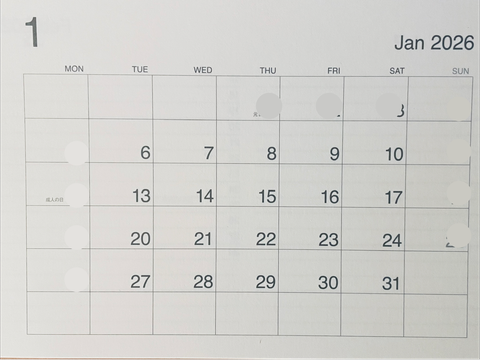
楽しさ、痛さ・辛さ、好き・嫌い、いい人・悪い人、疲れている度合い、これらが数値になって目に見える能力が欲しいか?と言われたら…欲しくないかもです
ぱっと見でわかったり、話していくことでわかったり、長い事関わりがあるとわかったりってこともある
…わかったつもりでいても本当は全然わかっていなかったり
そんなところも人間は面白いんだと思います