「なぜ人は自分を責めてしまうのか」

先日、信田さよ子さんの「なぜ人は自分を責めてしまうのか」を読んだ。
なぜ人は自分を責めてしまうのか。私はそのことがずっと気になっていた。
「自分のせいで」「私が悪いんだ」といった言葉はどうしてうまれるのか。
なぜ、どう考えてもあなたのせいではなさそうなシチュエーションで、自分を登場させて否定してしまうのか。
ここに書かれていたのは、そう合理性を持たせなければ生きてこられなかった人たちがいる、ということだった。
わかりやすい身体的な暴力や、精神的ないじめ”ではない”形で行われる、善良で上質でふわふわの真綿のような「支配」がある、ということを改めて突きつけられた気がした。
”ケアと暴力は紙一重です。”
この一文を、ナイフで自分を刺しながら読む。
子の立場で読むことも、親の立場で読むことも、お店の立場で読むことも、どの方向からも読む。
突然に殴られたり、理不尽に怒られたり、感情を否定されたり、親の機嫌で言動が左右したり、不条理な世界に放り出された場合、頭の中は混乱をする。なぜ、自分はこんな目にあうのだろう。そこに合理性を持たせなければ、生きていけない。
__抜粋__
”「そのなかを生きるのにどうしたらいいか。それには、たったひとつの合理性があるんです。この言葉さえ自分で覚えていれば、そういうなかを生きることができるんです。「すべて自分が悪い」
自分に包丁を向けられる。おじいちゃんかお父さんに首絞められそうになる。そういうときに、「自分が悪いんだ」と思えば、自分にとって説明がつくんですよ」”
_____________
そうして合言葉のように、生きるために「自分が悪いからこうなったのだ」と、自分を納得させる言葉をかけ続ける。
それはいつしか身体に浸透していく。そうすることでしか生きられなかった人がいる、ということに苦しくなる。
自分にとっては”愛”だと思っていたものが、別の誰かにとっては”支配”であることもあるのかもしれない。
自分にとっては”ケア”だと思っていたものは、相手にとっては”力を奪われていること”であるのかもしれない。
だからといって、誰も他者をケアしない社会にしたくはない。そうであるなら、自分に鋭い矢印を向け続けるしかない。
それは自分を責める矢印ではなく、自分が善良だと信じていることは、相手にとっても本当にそうであるのか?と疑う姿勢かもしれない。
自分を信頼しながら、自分を疑う、という姿勢かもしれない。
とっても勉強になる本だった。読んで良かった。
関連記事
コメント6件
矢印を明確にしすぎるのは「自己責任的」な考え方にもつながりそう。
矢印の起点をあいまいにして、その関係全体を柔らかく受け止められれば、相手にも自分にも優しくなれるのでは。積極的にあいまいにすることは決して無責任ではなくて、柔らかさと冷静さと強さを持った姿勢のような気がします。
幼少期安心安全と思えない環境で育つと、大人になっても常に緊張し、何かあると自分が悪いと思うようです
みんながそうであると思っていましたが、最近そうではないことを知りました
昔は、自分が存在しない方が世の中うまく回るのでは?と思っていたこともあります
めちゃくちゃ疲れます笑
先日職場で、”自分で手順書を貰ってくる”ことを出来るようにしなければならない人に、他の方がよかれと思って手順書を持って来てあげてました
私は持ってきてくれた方に、お礼と気がつくことへの賛辞を伝えようとしましたが、先輩は”彼が自分でやらなきゃいけないことなので、あなたがやらなくていい。自分の仕事をしてください”というようなことを伝えてました。
やってもらうことが当たり前になると、この先ずっとその人は誰かに助けて貰わないと生きていけなくなる、それに自分で何かしようとしなくなる、と先輩はおっしゃってました。
実際にその方は、蓋がはめられない時、私から見えるように体勢を変えて「出来ない」と独り言を言い続けてました。
(ちなみにその後、その方は自ら「手順書を下さい」と言えるようになりました)
本当に”ケア”と”力を奪うこと”は紙一重ですよね
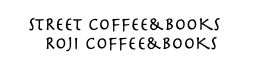

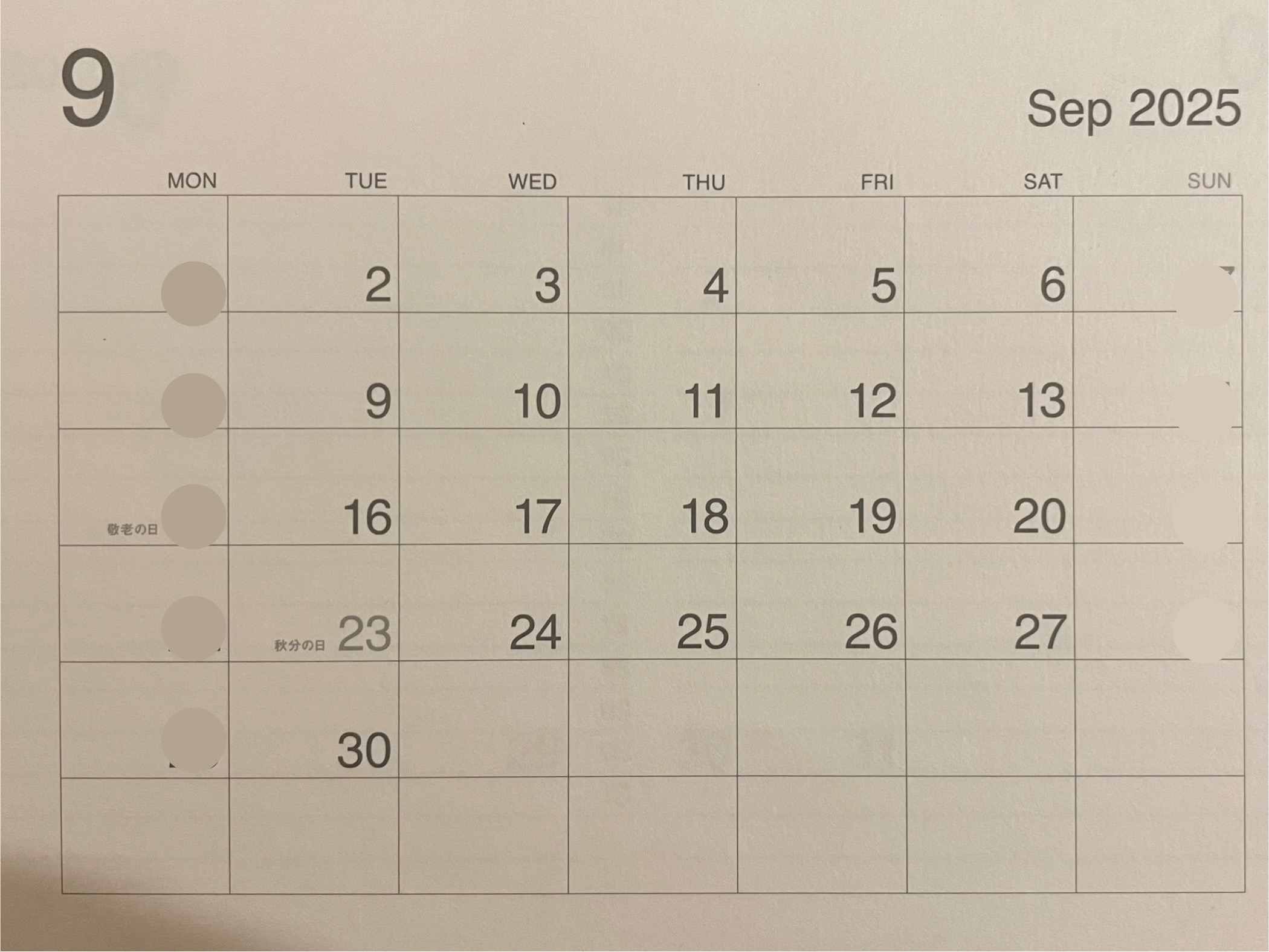






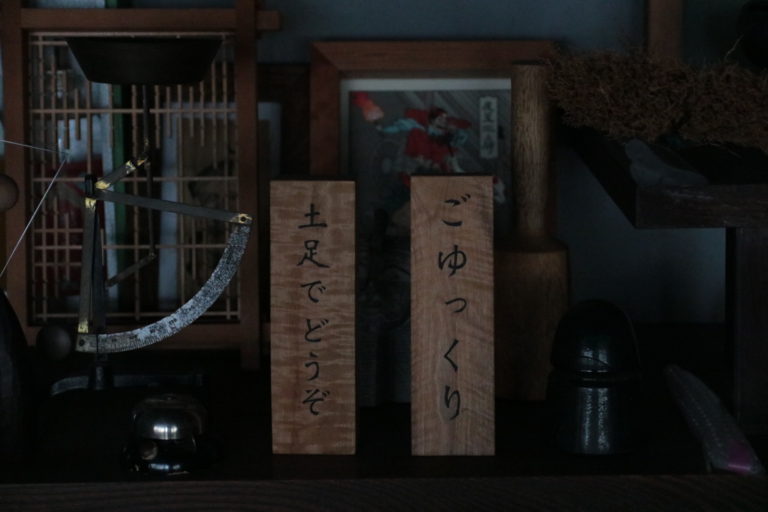
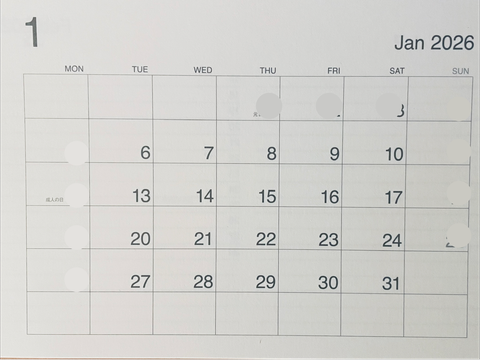
「自分が悪いから…」って人は優しい心の持ち主だと思う
自分が犠牲になれば周りがうまくいく、平常を保たれる、と思ってしまうのだろう
仕事でおじいちゃんおばあちゃんを車から施設に連れて行く
足腰が弱くて、車椅子だったら楽だし時間も短縮できるけど、トレーニングを兼ねて歩行を介助する
効率ばかりを追求してはいけないみたいだ
世の中の事象は何故そうなっているのか?背景を想像する力も必要なんだろう